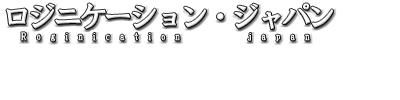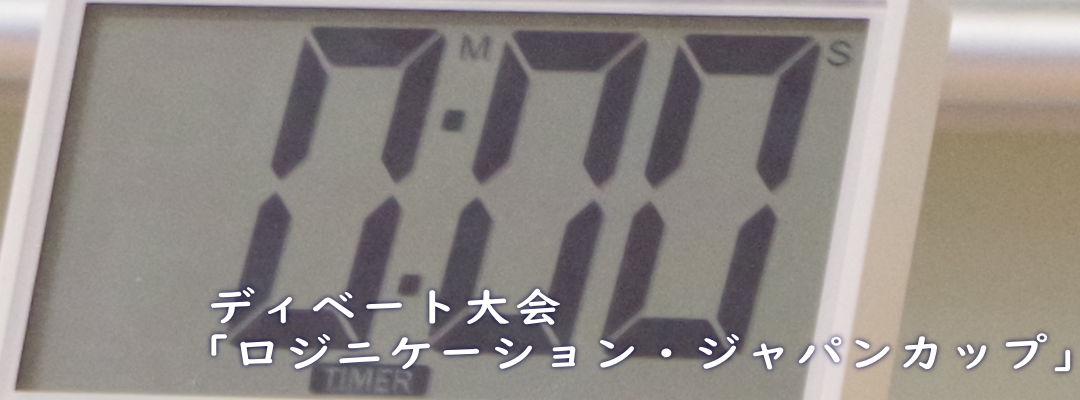「ディベート」ガイド
1.中高生の多くが取り組む「ディベート」とは
① ある与えられた論題(テーマ)に対して、 ② 肯定(賛成)側と否定(反対)側に機械的に分かれ、 ③ 発言時間が限られた各自のスピーチにより、 ④ 説得力を競う団体競技のこと。 |
× 自分の好きなテーマで話したり、自分の主義主張を述べたりする弁論大会
× 相手の発言に野次を入れたり、反論で遮ったりするテレビ討論会
× パワーポイントやグラフ、映像を使って説明するような、プレゼンテーション
2.当大会の試合におけるポジションについて
|
① あらかじめチーム全体で用意した立論を読み上げる「立論」 |
→各選手のスピーチの順番・役割・時間は決められており、質問に応答する時間帯以外は、1人の選手が話している最中に、他の選手が発言することはできません。
3.試合時間(当大会・約35分)
① 肯定側立論 3分
② 否定側立論 3分
準備時間 2分
③ 否定側質疑(肯定側応答) 2問
④ 肯定側質疑(否定側応答) 2問
準備時間 1.5分
⑤ 否定側反駁 2分
準備時間 1.5分
⑥ 肯定側反駁 2分
準備時間 1.5分
⑦ 否定側再反駁 2分
準備時間 1.5分
⑧ 肯定側再反駁 2分
準備時間 1.5分
⑨ 否定側最終反駁 2分
準備時間 1.5分
⑩ 肯定側最終反駁 2分
4.立論担当者の役割
立論は、様々な証拠資料を用いて議論を組み立てる必要があり、チーム全体での綿密な事前調査が求められるため、アドリブで発言することはありません。
→原稿を間違えず、滑舌よく、時には審判も見て、メモがとりやすいように読み上げることが求められるポジションです。
5.立論の構成
論題(テーマ):今回のディベートで議論する内容を表す。
・「日本は高齢者による自動車と原付の運転を禁止すべきである。是か非か。」
定義:今回の論題(テーマ)で用いられている言葉の確認をする。
・ここでいう「高齢者」とは70歳以上の人とする。
・ここでいう「自動車と原付の運転」とは道路交通法が適用される道路において同法が定める自動車または原動機付自転車を運転する行為とする。
プラン:どのように実行していくかを説明する。
・2018年4月1日から開始するものとする。
・道路交通法と関係法令を改正し、2018年4月1日時点で満70歳以上の者が保有する運転免許証は同日に失効し、同日以降に満70歳となる者が保有する運転免許証はその有効期間の末日または満70歳の誕生日のいずれか早い日に失効するものとする。満70歳以上の者への交付・再交付・更新は行わない。
→この大会では、付帯事項で定められた内容以外のプランを追加することを禁止するので、以上の内容は読み上げない。
<肯定(賛成)側>
ラベル:論題(テーマ)を肯定すると、どういうメリット(良い点)があるかを短い言葉で説明する
・「交通事故の減少」
内因性(現状分析):プランを採っていないために発生している問題があることを説明する。
・高齢者は事故をしやすい。
・高齢者による事故が多発している。
→特に高齢者が事故をしやすいことを説明しないと、高齢者の運転だけを禁止する理由が生まれない。
解決性(発生過程):プランを採用すればその問題は解決できることを説明する。
・高齢者が運転する機会がなくなるので、事故が起こらなくなる。
重要性:その問題がとても深刻であり、解決が求められていることを説明する。
・国民の生命を守るために、国は法律を変えなくてはならない。
<否定(反対)側>
ラベル:論題(テーマ)を肯定するとどういうデメリット(悪い点)が起きるかを短い言葉で説明する
・「高齢者の生活の圧迫」
固有性(現状分析):プランを採用しなければ発生しない問題であるということを説明する。
・車は高齢者にとって生活必需品。
・車を使って働いている高齢者も多い。
→今でも発生している問題であるならば、プランに問題があるとは言えない。
発生過程:プランの採用によって新しい問題がどのようにして起こるのかということを説明する。
・高齢者が運転できなくなるので、高齢者の移動手段や労働機会が奪われてしまう。
深刻性:その問題は論題を否定するほどの深刻なものであるということを説明する。
・高齢者の日々の生活を圧迫するプランは、生存権の侵害に当たる。
6.質疑担当者の役割
質疑は、相手の立論に質問するポジション
→どこに質問しているのかの「サインポスティング」をしっかり行いましょう。
→時間の管理権は質疑側にありますが、相手に悪意が見えない限り、答えは基本的にさえぎらずに聞きましょう。
① 相手の立論について、わからなかった点や疑問点を確認する
例)内因性の1つ目にお聞きします。高齢者による事故は、年間でどの程度発生しているのですか?
→審判や聴衆の代わりに質問するようなイメージ
② 相手の弱点をジャッジにアピールし、次の反論につなげる
例)内因性の2つ目にお聞きします。「高齢者は事故をしやすい」とありましたが、若い世代に比べて
事故をしやすい理由は説明されていましたか?
→反駁担当者ときちんと連携して、反駁につながるような質疑を心がける
7.応答担当者の役割
応答は、立論担当者が行い、立論に対する相手からの質問に答えるポジションです。
→相手の質問をはぐらかすことなく、誠実に答えましょう。
→自分たちの議論を小さくしてしまうような受け答えや、立論内容と異なった応答は厳禁です。
→チームとしての正しい受け答えができるような、想定応答の用意が不可欠です。
8.反駁・再反駁担当者の役割
反駁は相手の立論に対して、再反駁は相手からの反駁に対して反論していくポジションです。
→どこに反駁しているのかのサインポスティング、反論内容、証拠資料、まとめの順で行います。
→再反駁のパートで新たな反駁をすることはできません。
→証拠資料を読む時には、内容が聞き取れるようにわかりやすく読むことが重要です。
→使用した資料によって、自分たちは何を主張したいのかがジャッジに伝わるように努めましょう。
→相手のシナリオに沿いつつ、自分たちに有利な結論を導く「ターンアラウンド」ができないかも検討しましょう。
9.最終反駁担当者の役割
最終反駁は、試合をまとめつつ、自分たちの議論が相手よりどう上回っているかを主張していくポジションです。
→立論に沿って、反駁の流れがどうなっていたかの議論全体の確認をします。
→相手の反駁がなかった点を念押しし、反駁がぶつかり合った点について、こちらの方が上回っている説明をしっかりしておかなくてはなりません。
→明らかに負けている点は諦めて触れないという判断も必要で、反駁が見落とした点について反駁する「遅すぎる反論」や、立論で述べていない「新しい議論」を持ち出すのはルール違反です。
◎ 最も重要な役割は、ジャッジに対し投票理由の明示をすることです。
→自分たちの議論の中で一番効果的なものをジャッジに意識させ、この試合で重視すべき観点(国家としての役割・影響を及ぼす規模・発生確率など)及びその理由、そしてその観点に照らして自分たちが勝っているということを、論理立てて述べなくてはなりません。
→投票理由の明示がなされないと、ジャッジが自分の価値観に照らし合わせて判断してしまうことになり、試合を制御できなくなるので、確実に自分達に投票してもらえるような基準を打ち立てることが求められます。
10.フローシートとは
議論の流れを記録していくメモ用紙のことを、フローシートと呼びます。
→パートごとに何が話されたかメモを取り、そこからの議論の発展や質疑の様子などを記録していきます。
→発言中に考えることはせず、速記者のようにただメモを取ることに専念するとよいでしょう。
→記号などを使用して無駄な時間を取らない工夫もしておきたいところです。
11.判定の基本
① 試合の中で出された議論やそれに対する反論を聞いて、肯定側の主張するようなメリットが本当に生じるのか、その可能性はどのくらいの確率か、起こるとしてどのくらい大きなものと考えられるのかを評価します。
|
【メリットの評価】=【内因性】×【重要性】×【解決性】・ →簡単に言えば【メリットが起きたときの大きさ】×【起きる確率】 |
② 試合の中で出された議論やそれに対する反論を聞いて、否定側の主張するようなデメリットが本当に生じるのか、その可能性はどのくらいの確率か、起こるとしてどのくらい大きなものと考えられるのかを評価します。
|
【デメリットの評価】=【固有性】×【発生過程】×【深刻性】 →簡単に言えば【デメリットが起きたときの大きさ】×【起きる確率】 |
③ メリットの合計とデメリットの合計の比較を行い、主に第二反駁で出される両チームの比較・総括スピーチを参考にして議論を比較検討してどちらに投票するかを決定します。
12.反駁の評価
① 一方のチームが根拠を伴って主張した点について、相手チームが受け入れた場合、あるいは反論を行わなかった場合、根拠の確からしさをもとに審判がその主張を採るかどうかを判断します。
→反論のなかった部分については、基本的には同意されたものと見なしますが、そもそも当初から立証責任が果たされていなかったと考えられるものについては、反論がない場合でも却下して構いません。ただし、その際は選手に「なぜダメだったのか」を納得させられるような理由が必要であり、求める立証責任の基準は両チームに対して公平でなくてはなりません。
② 一方のチームの主張に対して相手チームから反論があった場合には、審判は両者の根拠を比較してどちらの主張を採るかを決定します。
13.判定説明
① 個々の論点などの判断
両チームの主張が対立した論点については、一方の主張を採用した理由(あるいはどちらの主張も採用しなかった理由)を、それぞれの発言を引用しながら具体的に説明します。審判の判断で採用しなかった主張については、採用しなかった理由を具体的に説明します。
② 個々のメリットやデメリットについての判断
メリットについては内因性・解決性・重要性、デメリットについては固有性・発生過程・深刻性のそれぞれについて、どのように判断したのかを具体的に説明します。
③ 全体の判断
メリットの全体とデメリットの全体のどちらが大きいと判断したかの理由を、具体的に述べます。第二反駁などで比較の議論が出ていた場合には、その議論にも触れて説明する。特に、比較の議論とは逆の判断をした場合には、なぜ逆の判断をしたのかを丁寧に説明します。
14.コミュニケーション点
話し方、スピーチの構成、スピーチの姿勢、スピーチの速度などを総合し、分かりやすいスピーチであったかを評価します。各審判はコミュニケーション点を各ポジション5点満点で自由に判断してよいのですが、点数はおおむね3点を平均とした正規分布となるようにつけなくてはなりません。つまり、3点より高得点・低得点となるほど出にくくなるように採点基準を設けるようにする必要があります。